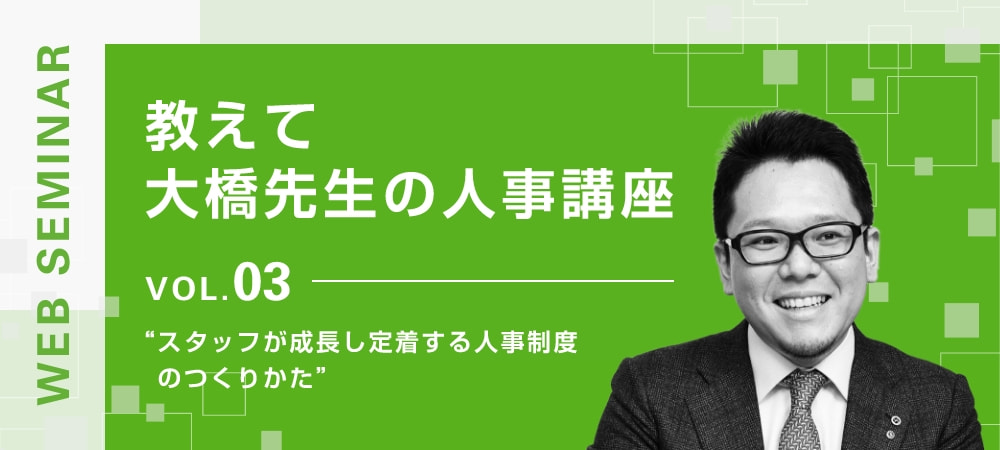
『教えて 大橋先生の人事講座』第3回目のテーマは「スタッフが成長し定着する人事制度のつくりかた」です。
人事コンサルタントの大橋高広先生にお話いただきました。
セミナー講師

大橋 高広先生
- 同志社大学を卒業後、大手通信系企業にて新規開拓営業を担当
- 経済団体にて中小企業の経営支援を担当
- 中堅製造業にて総務・人事・経理等のバックオフィス業務を担当
- 株式会社NCコンサルティングを設立、同社代表取締役社長に就任
- 関西経済同友会 会員
- 大阪商工会議所 人事労務サポート推進パートナー
- 八尾商工会議所 専門相談員
- 守口門真商工会議所 専門相談員
- 和泉商工会議所 専門相談員
セミナー動画
モリタ友の会有料会員に登録するとセミナー動画がご覧いただけます。
講演内容
では、さっそく始めていきましょう。
職場の現状を把握する
人事制度をつくる際、非常に大切なのは現状を把握することです。もちろん、先生ご自身が思い描いている理想に近づけるということは言うまでもありませんが、それに加えて、院内で働くスタッフの意見や考え方を理解し、職場の問題や課題を捉えて設計していくことを強くおすすめしています。
医院主導で設計するより、現場の問題を踏まえて設計したほうが高い効果が出るということは、今起こっている問題に対して直接アプローチしていくことができるということに他なりません。そこで、私が提案しているのがこの15のテーマです。
 この中から特に注目してもらいたいテーマを紹介します。まずは、1)の役職・配置について。リーダーや主任、事務長など、すでにいろいろな形で決められているかもしれませんが、ここで私が問いたいのは、“本当にマネジメント適性を持った人が役職に就いていますか”ということです。実務のスキルがどんなに高くても、マネジメント能力の低い人やリーダーシップのない人が役職に就いているとしたら、職場で問題が起こっているかもしれません。
この中から特に注目してもらいたいテーマを紹介します。まずは、1)の役職・配置について。リーダーや主任、事務長など、すでにいろいろな形で決められているかもしれませんが、ここで私が問いたいのは、“本当にマネジメント適性を持った人が役職に就いていますか”ということです。実務のスキルがどんなに高くても、マネジメント能力の低い人やリーダーシップのない人が役職に就いているとしたら、職場で問題が起こっているかもしれません。
2)の基本給と3)の賞与は、高ければ高いほど満足するかもしれませんが、昇給して喜ばしい気分に浸るのはせいぜい1ヵ月か2ヵ月。その後はそれが当たり前になって、昇給への感謝の気持ちは消えてしまいます。ですから、評価制度をきちんと作ることが大切なのです。「1年間勤めたから1万円上がります」ということではなくて、「こういう努力をしてこういう成果が出たからそれを評価して1万円上がります」ということにすると、その効果は感覚的に消えません。
6)の休日・休暇、7)の残業も、それぞれの課題をしっかり確認しておかなければならないところ。8)の人事評価も大切なポイントで、中でも“誰が評価するのか”ということについては、よりしっかりチェックしてもらいたいと思います。評価については直属の上司の判断がすべてとしているところも多いのですが、もし部下が上司に対して何らかの不満を抱えていて、たとえば、「この人には判断されたくない」とか「この人に私の努力が本当にわかるんですか?」というふうに思っていたら、どんな評価基準をつくっても結局うまく機能しないということになってしまいます。ですから、“誰に評価してもらいたいか”については、特にしっかり確認すべきでしょう。その希望が現状にマッチしていなければ、上司を変えるのも一つの方法ですし、投票制にしてスタッフ同士で評価し合うという方法もあります。
次は11)の採用です。ここで現場の皆さんに確かめてもらいたいのは、“自分のクリニックで活躍できそうなのはどんな人ですか”ということです。社風や風土はクリニックによって違いますから、それを把握した上で、どんな人だったら活躍できそうか、ハキハキ物を言う人なのか、言われたことをきっちりこなす人なのか、そのあたりをきちんと捉えてほしいと思います。職場の風土に合っている人を採用する、それが採用のいちばんのポイントです。
等級制度をつくる
等級というのはランクのことで、簡単にいえば、スタッフをランクづけしましょうというのが等級制度です。ランクのつくり方は3つあります。まず一つ目が、能力で決める職能資格制度。能力を軸とする評価制度の場合、長く働けば基本的能力がストックされていくので年功式になりやすいというという特徴があります。ですから、年功的な雰囲気にしたい場合は、能力のストック型でランクをつくると良いでしょう。
次は、職務で業務を決めていく職務等級制度。これは、“この業務ができればこの年収になります”という成果主義のこと。悪くはない制度ですが、成果主義になると「あの人のほうが稼いでいるのになぜ私が手伝わないといけないんですか」という意見が出たりして、院内のチームワークが崩れるかもしれません。ですから、チームワークという観点で捉えたときに“本当にこれでいいのか”ということはしっかり考える必要があると思います。
最後は、役割等級制度。これは、人材育成や納期に関する役割を主任やリーダーに与え、その役割に基づいて等級を決める考え方のことです。役割を規定するとどうなるかというと、おそらく「人材育成をしてください」という話になるので、行動主義になります。ですから、行動を促したい場合は、この制度を採用することがおすすめです。
ほかにも、助手や受付のスタッフに、“歯科の知識を身につけてください”ということもあるかもしれません。それも能力の一つとして捉えることができるし、“早く習得してください”ということであれば役割と捉えることもできます。
歯科業界では職種によってやるべきことが異なるので、求めることを細かく記したランク表を職種ごとにつくってほしいと思います。
人事評価制度をつくる
人事評価制度について、ここではオーソドックスな3つを紹介します。
 一つ目は、売上や利益など、数値化できるものを評価に入れる業績評価。コンサルテーションからの成約を評価するというパターンもあります。
一つ目は、売上や利益など、数値化できるものを評価に入れる業績評価。コンサルテーションからの成約を評価するというパターンもあります。
能力評価については、たとえば自費治療の契約を取るときの話し方やアプローチの仕方、メソッドを評価するということ。業務の遂行に必要な能力を有しているかどうかを見るわけですから、ロールプレイングなどでも確認できると思います。
モリタ友の会有料会員に登録すると引き続き全文がご覧いただけます。

大橋からのお願い
本プログラムを受講された後、必ず何か1つでも実践してみてください。
何か行動を起こせば必ず未来は変わります。
このたびのご縁を大切に私自身も日々自己研鑽に励んでまいります。
ぜひ皆さまで一緒に頑張ってまいりましょう。

 等級というのはランクのことで、簡単にいえば、スタッフをランクづけしましょうというのが等級制度です。ランクのつくり方は3つあります。まず一つ目が、能力で決める職能資格制度。能力を軸とする評価制度の場合、長く働けば基本的能力がストックされていくので年功式になりやすいというという特徴があります。ですから、年功的な雰囲気にしたい場合は、能力のストック型でランクをつくると良いでしょう。
等級というのはランクのことで、簡単にいえば、スタッフをランクづけしましょうというのが等級制度です。ランクのつくり方は3つあります。まず一つ目が、能力で決める職能資格制度。能力を軸とする評価制度の場合、長く働けば基本的能力がストックされていくので年功式になりやすいというという特徴があります。ですから、年功的な雰囲気にしたい場合は、能力のストック型でランクをつくると良いでしょう。